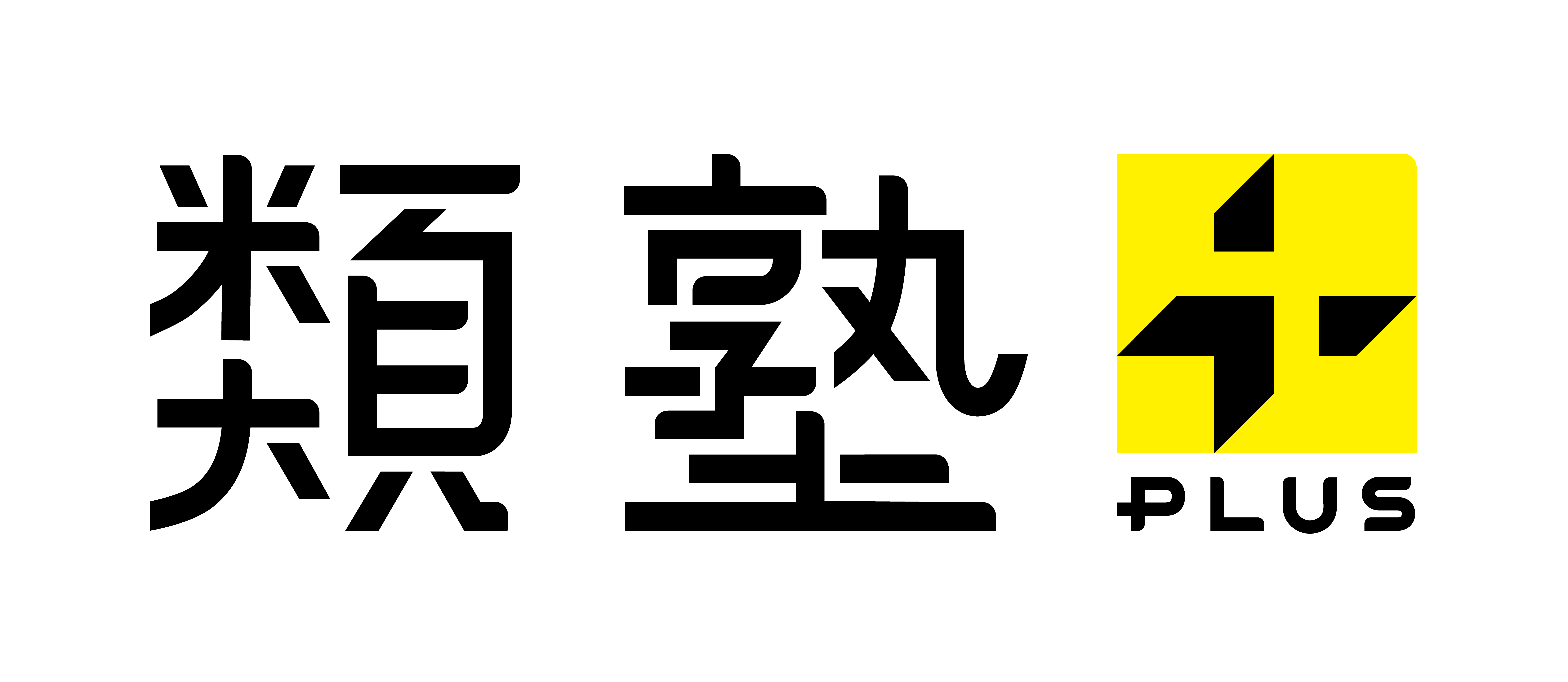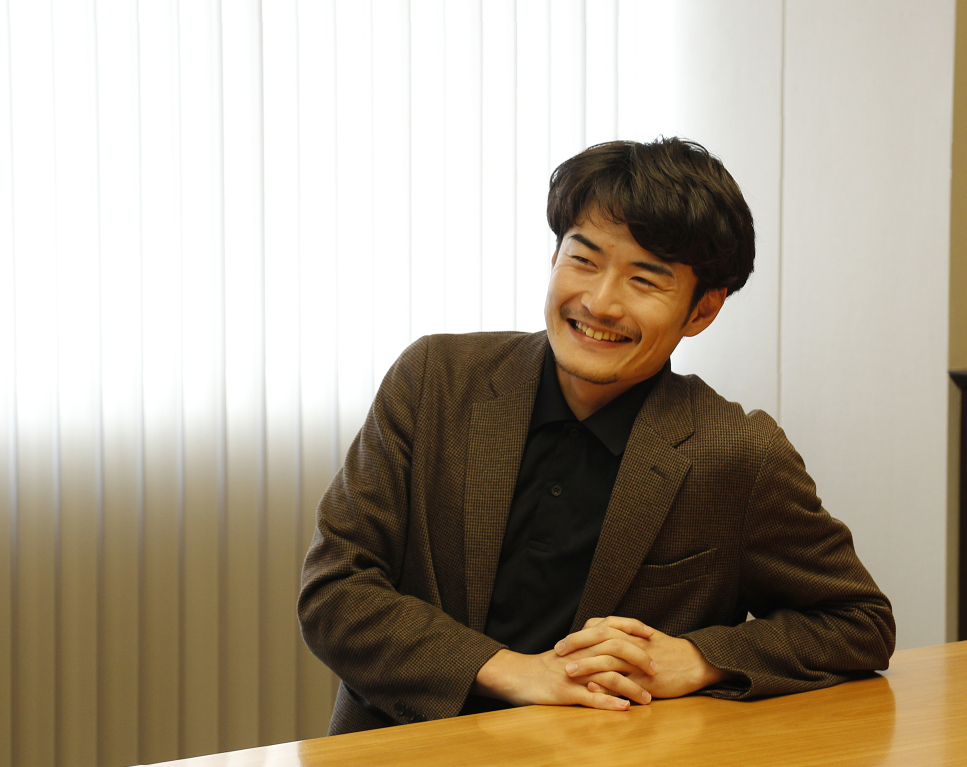創設50年を機に、時代の変化に合わせてリブランディングした、大阪の進学塾「類塾プラス」。
教育現場にとどまらず、営業・広報など多様な分野で活躍する若手人材が育っており、時代に合った新しい教育のかたちを追求しています。今回は、その中核を担う3名に話を伺いました。
それぞれの視点から見た類塾プラスの事業内容とは、どのようなものなのでしょうか?詳しくお伝えしていきます。
類塾プラスへの入塾、類設計室への入社を検討されている方は、ぜひこのインタビューを参考にしてください。
インタビュー対象者
- 前田敬成: 2020年入社 営業広報課
- 片山隼: 2021年入社 教室長
- 宮坂陽菜: 2022年入社 文系講師
-Q.はじめに、自己紹介とお仕事の内容を教えてください。
前田:
前田敬成と申します。入社6年目で、類塾プラスの営業広報を担当しています。 入社後4年間は文系講師として働いていましたが、昨年から営業広報担当となりました。

昨年、類塾は「類塾プラス」に名前を改め、リブランディングを行っています。「類塾が新しく類塾プラスに変わったこと」をアピールする広報活動が主な業務です。
他に、教室での営業活動において、スタッフが働きやすくなるよう、営業の運営を支える活動もしています。
営業と広報、それぞれの分野で仕事に取り組んでいます。
片山:
片山隼と申します。入社5年目で、文系講師からスタートしました。
2年目からは新規開校教室の教室長を務めていました。今年からまた教室が変わり、現在も教室長として活動しています。

仕事内容は主に、教室の営業方針の策定や、スタッフのモチベーション維持といった管理業務です。地域に向けた類塾プラスの営業・集客にも関わっています。
授業も担当していますが、教室長として大切にしているのは、教室全体を良くしていくこと、そして一緒に働くスタッフが成長できるかということです。
宮坂:
宮坂陽菜と申します。入社4年目で、文系講師として働いています。

日々子どもたちと楽しく授業をする中で、どうしたら成績を上げられるか、意欲的に取り組めるかを考えています。
子どもたちの「わかった!」「できた!」という瞬間が何よりのやりがいです。日々の関わりを通じて、一緒に成長できるよう努めています。
-Q.なぜ類設計室の教育事業部で働こうと思ったのか、理由を教えてください。
片山:
もともと大学時代は教育関係を学んでおり、それがきっかけで小学校の教員になりたいと思っていました。
類設計室の教育事業部で働きたいというよりは、「類設計室って面白そうだな、関わりたいな」という思いがスタート地点です。
さまざまな企業のインターンシップに参加しましたが、類設計室では「働くって何だろう」ということをグループワークやディスカッションでとことん話し合いました。それが印象に残っています。
また、社員をとても大切にしてる企業だと感じ、魅力的だと思いました。給与や休みだけでなく、私たちが今後40年間働くことをしっかり考えてくれている企業だと感じたからです。
仕事に没頭し、やりたいことに専念できる環境も、魅力的な特徴です。
-Q.一日のお仕事の流れについて教えてください。

宮坂:
まず授業準備から始めます。16時くらいになると、学校が終わった子どもたちが自習室に来てくれるので、そこで一緒に宿題に取り組みます。
授業外で子どもたちと関わる貴重なチャンスで、学校や遊びのことを話したり、生徒面談したりしています。帰宅するのは22時~22時半ごろですね。
片山:
私もスケジュールはほとんど同じです。あとは、授業のコマが入っていない時間に保護者の方と面談をしたり、授業の様子をお伝えする電話をかけたりしています。
前田:
私も授業は担当していますが、2人とは異なり、平日は基本的に広報と営業の仕事をしています。
類塾プラスのリブランディングはもちろん、さまざまな会社と連携しながら広報の仕事をするのでそういったディレクション業務が多いです。
プロジェクト型の仕事なので、毎日スケジュールが異なります。基本的には12時に出社し、21時ごろに業務が終了します。教室や現場によって1時間ほど前後することもあります。
-Q.広報という視点から、塾業界の変えていきたいところはどんなところでしょうか?
前田:
私個人の考えとしては、やはり「人の集まる場や空間を作っていきたい」という思いがあります。

類設計室には、類塾プラスという教育事業の他に、農園事業や設計事業もあります。 複数の事業で幅広く活躍していきたいと思い入社した経緯がありました。
現在、リブランディングを進める中で広めていきたいのが、「教育は、社会構造の変化と密接に関わっている」という点です。
たとえば今ならAIが発達していて、AIなしでは仕事が回らないという時代に突入しています。 他にも、日本では少子高齢化や人口減少が深刻です。それにより働き方が大きく変わっていく時代でもあると思います。
今後10年、20年と人生を歩んでいく際、限られた時間の中で何に時間を費やしていくのか、というところが重要です。それは大人だけでなく、子どもも同じだと思っています。
勉強は、進路を切り開く一つの要素としてとても重要です。 子どもたちのために、「自分の強みや資質を活かして社会に貢献すること」や「どうすれば仲間や周りの人の役に立てるのか」を考える環境を作っていきたいと思っています。
当たり前のことを当たり前と思わず、自分たちで作っていくという意識を持ってもらえるような教育を提供していけるようになりたいです。
-Q.日々、どういう思いで働いていらっしゃいますか? 日々の仕事を通して感じていること、仕事をする上で大事にしている考えを教えてください。
片山:
さまざまな仕事をしていく中で、何度か自分の価値観を「ぶっ壊される」瞬間がありました。
たとえば、先ほど「活力」や「働き方」という話をしましたが、もともと自分の中でそういったものはあまり重視していませんでした。やることが決まっていたら黙々と進めるタイプだったんです。

しかし、今年教室が変わり、生徒さんや一緒に働くメンバーも変わって、人によってモチベーションは重要だと気づきました。
ですので、子どもたちが楽しいと思える授業はもちろん、説明会でも、わざわざ足を運んだ価値があるかどうかということを大切にするようになりました。
足を運んでくださった方たちの心がどう動くのか、どうすればプラスの方向に変えていくことができるのか。そういうところを意識して取り組んでいます。
-Q.類塾プラスは「教育事業である以前に社会事業である」という信念を大切にされていると伺いました。育成機関として社会と子どもたちを断絶せずにやっていくために、どんなことを伝えていきたいですか?
前田:
一人ひとりに活躍できる力があり、誰かに貢献できる力があります。
今の教育業界では、テスト・勉強・点数に重きが置かれていて、子どもたちはテストの結果で評価されてしまう環境にあります。
その中でも、粘り強く考えることや、最後まで諦めずに考えることなど、さまざまな視点を持って取り組めるようになってほしいです。
しかし、子どもたちは点数で評価されないと自信が持てません。そのため、面談では「君にはこういう強みがあるんだよ」「こういうところで周りの役に立てるんだよ」ということを伝えるようにしています。
勉強に取り組む姿勢やプロセスの中で、自分だけの強みを見つけ、自信を持ってほしいと思います。

-Q.子どもたちのモチベーションを高めるために意識的に取り組んでいることはありますか?
片山:
「丁寧に言葉を紡ぐ」ことを意識しています。
今まで、子どもたちが相手でも保護者の方が相手でも、私は思ったことをすぐに話すタイプだったのですが、それを一度文字に書き出したり、どう伝えれば良いか考えたりするようになりました。
また、授業内で授業と関係ない雑談をすることもあります。
子ども同士で褒めあったり、自分の生活や仕事での気づきを話したりするなど、そういった考える時間や余白を作るようにしています。
-Q.現代の子どもたちの心の中はどうなっていると思いますか? 日々子どもたちと接する中で、思うことがあれば教えてください。
宮坂:
なかなか素直になりきれない子が多いな、というのは現場で働かせてもらっていて感じます。
試験の結果や日々の学習態度について、私が「すごく頑張ったね」と声をかけると、「期待するような結果が出せなかったらどうしよう」と不安に感じ、素直に喜べない子が少なくありません。

しかし、そうやって自分を抑えながらも、心の底では褒められたい気持ちがあります。思春期の中学生の男の子でさえ、褒められることに対しては少し照れながらも、良い評価をまっすぐに求めている子がたくさんいます。
以前は、できていない部分を指摘することもありましたが、最近はとにかく褒めるようにしています。
保護者の方には、「教室ではこのように頑張っていますよ」とお伝えするようにしています。 家で見せる顔と教室で見せる顔は、やはり少し違うと思うので、教室での様子や頑張り、成果を具体的に伝えることで、保護者の方の安心につながっています。
授業内では、授業準備に時間をかけるようにしています。 また、子どもたちがもっと知識をつけたくなるような仕掛け作りも意識しています。
「授業でこのように伝えよう」ということをしっかり考えてから授業に入るようにしていますね。
-Q.子どもたちの成績を上げるために意識されていること、努力されていることは何ですか?
宮坂:
どれだけ時間を使ってその子と関わっていけるかが、すごく大事だと思っています。
たとえば、休み時間に勉強が楽しいか、正直な今の気持ちを聞くことがあります。 事務室の前のカウンターで話すようなことだけでなく、今子どもたちがどういう気持ちで教室に来てくれているかを、一人ひとりに聞いて知っていくことが重要だと思います。
自分の学生時代は、塾に嫌々行っていましたが、類塾プラスでたくさんのお子さんと関わる中で日々のコミュニケーションが大事だということに気づきました。
-Q.子どもたちのどのような部分を見ていますか? また、具体的な働きかけについて教えてください。
宮坂:
まずは塾へ来たときの「こんにちは」の声の大きさと表情を見ています。
たった一言ではありますが、暗いなと思って話しかけに行ったら、実際に学校で嫌なことがあったり、不安なことを話したりしてくれます。 そのため、まずは声や表情に注目するようにしています。

働きかけについて具体例を挙げますと、ある小学五年生の女の子と面談した時のことです。 その子は、「実は音読を頑張りたいんだ」と教えてくれました。
すでにとても上手だったので「今でも十分上手だよ。もっと上手になりたいなら、一日一回でもいいから、家で練習してきてごらん」「今のまま練習していけばさらに上手になるよ」と声をかけました。
すると、次の週の授業から、その子の声の大きさと口の開き具合と前のめり感が、目に見えて変わりました。 やはり褒められてすごく嬉しかったのだと思います。
その話がきっかけで、向こうから勉強以外のことも色々な話をしてきてくれるようになりました。 声をかけることの大切さとともに、こんなに変わるんだというのを実感しました。
-Q.受験や教育制度の変化について、率直なご意見をお願いいたします。
片山:
日々子どもたちと接していて、今まで大人が良しとしていた教育や、自分たちの成功体験から導き出す教育は、5年10年後には通用しなくなると感じています。
類塾プラスとしては、「なぜ学ぶのか」「どう使えるのか」という目的と意味を重視する教育を提供し、子どもたちが社会へ羽ばたいていく過程をしっかり支援していきたいと思っています。
-Q.最後に、今後の夢や目標について教えてください。

前田:
広報課なので、普段チラシを出したり、ホームページで情報発信をしたりしている中で、「こういう意味を込めているんですよ」ということが伝わったら嬉しいです。
また、対面で何かをしていくことの良さを感じているので、人が集まる空間としての「村」を作りたいと思っています。
私自身、人のつながりが深い地域で育ったので、さまざまな人に育ててもらったなと感じています。 たくさんの大人と触れ合う方が、教育というシステムもうまく回っていくし、地域も活性化していくと考えています。
類塾プラスはさまざまな変遷があり、課題もあります。 地域や社会、ひいては日本・世界から「共感・応援される組織でありたい」というのが、一つの大きな目標です。
片山:
教育というのは、次世代の国、次世代の世界を作っていく営みだと思っています。
今の子どもたちも、受けた教育によって次の世代にどのような教育を受けさせていくかが変わります。やがてそれが地域をも作っていくでしょう。
どのような環境だと育てやすく、どのような場なら健やかに育つのか、子どもたちと考えながら作ることができるようになりたいです。
宮坂:
ずっとワクワクしていたいなと思っています。
子どもたちから見て、「こういう大人になるんだったら、別になってもいいかもな」と思ってもらえるようになりたいです。
子どもは、思った以上に大人のことを見ています。
ずっと何かにワクワクしている大人を見て、子どもたちに「大人って楽しそうだな」「仕事って面白いのかな」と憧れを抱いてほしいです。
まとめ
今回は、大阪にある類塾プラスの前田さん、片山さん、宮坂さんにインタビューをしました。
教育事業部に所属する3名ですが、それぞれ違った視点から、類塾プラスの事業内容についてお聞きすることができました。
今回のインタビューを通して、類塾プラスの若手社員の方々が、教育という枠に留まらない広い視野と社会への強い当事者意識を持ち、自らの役割を創造しながら活躍されている姿が印象的でした。
子どもとの関わりを特に大切にされており、多くの方と接する機会は子どもにとっても貴重な経験であり、思い出になると思います。
教室での様子は保護者の方にも伝えてもらえるので、安心できるでしょう。 子どもだけでなく、働くスタッフや地域の人々を大切にし、国や世界からの注目も意識してリブランディングを進めています。
今後、類塾プラスがどのように発展していくのか、多くの方が期待を寄せているでしょう。
このkaiというメディアでは、様々な企業のサービスや社内環境について、多数回答をいただいています。興味をお持ちの方は、ぜひ一度、口コミの回答を確認し、入社の判断材料にしてみてください。