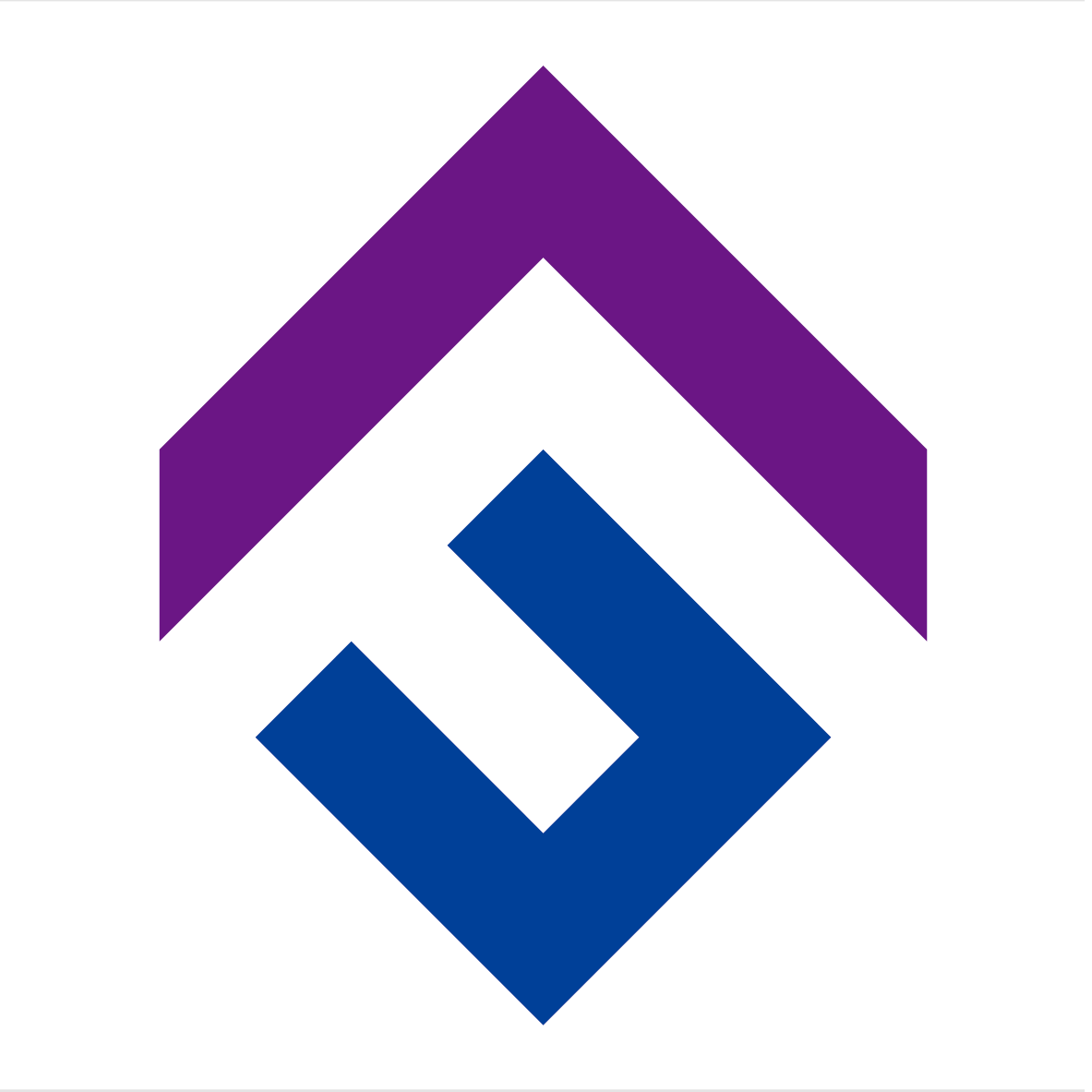非正職員向けの相談窓口について
研修・教育・フォロー体制2025年6月16日 公開

「受けたい研修を受けられず、上司の対応に不満を感じた」という非正職員の口コミを見ましたが、実際はいかがですか。また、非正職員が上司に不満を感じた場合に相談できる窓口はありますか?
深代税理士法人の採用担当です。貴重なご質問をいただきありがとうございます。
「受けたい研修を受けられず」との口コミに関し、研修の受講を上司が一方的に不許可とすることはありません。
しかしながら、繁忙期の業務状況、本人のスキルレベル、現在の業務との関連性などを総合的に考慮し、研修のタイミングや内容について相談・調整させていただく場合があります。
これは、あくまで効果的にスキルアップしていただくための確認であり、受講を制限する意図ではありません。
この点につきまして、ご理解いただけますと幸いです。
弊社では、正職員・非正職員の別なく、下記の研修を受講可能です。
すべての研修は録画されており、いつでも視聴できますが、効果的な学習のため、段階に沿った順番での受講をお願いしています。
・1年目研修:入社1年目の全職員(新卒・中途、正職員・非正職員を問わず)が対象です。
以前は受講時期が限られる場合もありましたが、現在は全ての研修内容を録画しているので、自身のタイミングでいつでも受講・復習が可能です。
・法人研修:お客様先への訪問を希望する職員が、上司と相談の上で受講します。
(業務上、訪問業務を行わないと判断された場合は、他の研修をお勧めすることがあります。)
・資産税研修:原則として入社2~3年目以降で、研修内容を理解できる一定のスキルレベルに達した職員が対象です。
例えば、自身のスキルレベルに比して高度な研修をご希望の場合、上司の判断により、現在の業務に関連の深い研修や基礎的な内容から受講してもらうよう調整することがあります。
一例として、相続分野の専門知識を習得する『資産税研修』への参加を非正職員の方が希望された際に、本人のスキルレベルを考慮し、まずは基礎知識の習得を優先するよう促すケースなどがこれに該当します。
これらの受講基準や背景にある考え方について、これまでは主に管理職間で共有しており、従業員への説明が十分でなかったと認識しています。
その結果として、「受けたい研修が受けられない」といった誤解や不満を生んでしまった可能性があるのであれば、申し訳ございません。
この点を真摯に受け止め、今後は受講基準を全従業員に明確に周知徹底するとともに、必要に応じて管理部門が受講に関する調整をサポートする体制の構築も検討してまいります。
また、上司の対応について不満がある場合は、社内に設置しています衛生委員会に意見出すことができます。
相談内容は、担当者がヒアリングを行い、実態を把握した上で対策を進めていきます。
全職員が意欲的に働けるよう、今後も職場環境の改善に努めてまいります。